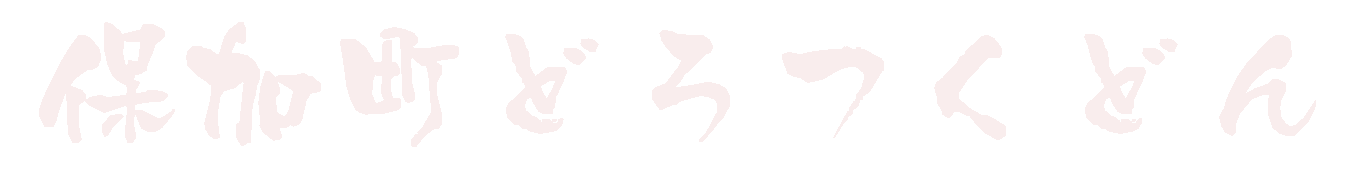語り部の章 ― はじまりの記憶 ―
北川新十郎や古老の語る、どろつくどん誕生の物語。
- 「どろつくどん」の起源は、文政8年(1825年)〜文政9年(1826年)頃、三柱神社が現在地へ遷座した際の造営・奉納行事中に生まれたと言われています。
- 保加町(外町)に属する問屋・町人街が、この遷座式の機会に「山車を出して興を添えよう」と働きかけ、のち、各町内が参加したとされています。
- 北川新十郎(保加町所属)および弥永久右衛門らが、江戸・神田明神の「葛西囃子」や京都の山鉾構造を参考に、山車と囃子を刷新。翌年の奉納で大好評を博し、以降「どろつくどん」として定着しました。
保加町の語り部たち ― 伝承と誇り ―
祭りを受け継いできた人々の声・思い・語り。
<音に宿る語り ― 太鼓と笛が伝えるもの >
保加町どろつくどん以外の町内も囃子や山車にも、その町内独自の伝承された囃子の調子や踊り方があり、各町内は伝承を続けている。
保加町どろつくどんでは、三柱神社への奉納時などに用いられる最も重要なお囃子として、通称「チャクチャク」があります。この「チャクチャク」は、奉納の際に欠かせないお囃子であり、保加町どろつくどん独自の伝統として、町内で伝承される者にしか教えられない門外不出の調子が存在します。
お囃子の編成は、大太鼓1台、銅鑼1台、小太鼓2台、笛4管〜5管、摺り鉦1台で構成されます。山車(祭り関係者は「ヤマ」と呼ぶ)の取り扱いは非常に厳格で、子ども時代から大人たちによって「大切に使うこと」を厳しく教えられます。
どろつくどんの起源は文政9年(1826年)に遡りますが、当時のものが全て残っているわけではありません。しかし、お面の割れや古い和紙、古図などの資料が発見されており、先人たちから大切に受け継がれてきたことが現在まで伝わっています。
「チャクチャク」に続いて、町内(現在の柳川市内)を巡回する際には、**道中囃子「ドロツク」があります。また、神社の参道(拝殿へ向かって伸びる道)に差し掛かる際には、「チンツク」**というお囃子が用いられます。どこからが参道かは、昔からの言い伝えを守りながら巡行しています。
保加町どろつくどんでは、**大太鼓を打つ役職は「上山宰領」**と呼ばれます。その年に任命される上山宰領は、上山(お囃子・踊り・鉾上げ)の総括責任者として、奉納・角付け・曲がり角での囃子の調子を決め、山車方(山車の引き回し)との連携も担います。
半世紀以上、保加町どろつくどんに関わり、先輩の上山宰領に師事してきた経験からも、それぞれのどろつくどんに対する思いや伝承していく志には、深く感動させられます。
<まつりを語る ― 三柱神社への奉納 ―>
三柱神社はもとより、保加町にも、氏神様として天満宮の分霊神社があります、どろつくどんの山車が保加町町内から出るとき、帰ってきた時には必ず奉納四面として、チャクチャクでの奉納を行います。その奉納四面についてご説明しましょう。
物語のあらまし
- 太陽神である 天照大御神(あまてらすおおみかみ)は、弟神 須佐之男命(すさのおのみこと)の乱暴な行為を憂い、ついに天の岩屋(「天石窟/あまのいわや」)に入り、磐戸(いわと)を閉じ籠ってしまわれます。
- 天照大神が隠れてしまったことで、世界は光を失い、昼と夜も分からない常闇の状態となりました。
- 八百万(やおよろず)の神々が相談の場「天安河原/あまのやすのかわら」に集まり、天照大神を岩戸から出す方法を考えます。
- 知恵の神 思兼神(おもいかねのかみ)が提案し、神々は音楽や舞・囃子を用いて岩戸前を賑やかにします。特に女神 天宇受売命(あめのうずめのみこと)は踊りを舞い、岩戸の外の様子を面白おかしく演出しました。
- 興味を惹かれた天照大神が岩戸を少し開けた隙に、力の神 天手力雄神(あめのたぢからおのかみ)が岩戸を開け、天照大神を外の世界へと引き出します。
- 世界に再び光が戻り、闇の時代から明るさが回復され、秩序が復されます。
未来への語り部 ― 伝統をつなぐ若衆たち ―
次の世代へと伝えていく活動・思い・取り組み。
上記が天岩戸神話と奉納四面の関係は、天岩戸神話(春斎年昌 画)の左側にいらっしゃる
①猿田彦大神が奉納四面で最初に舞う「天狗の面」です。猿田彦大神の主な役割は、天照大神の孫である邇邇芸命(ニニギノミコト)が地上に降り立つ際に、道案内とされています。
続いて、「お多福面」は②天宇受売命(あめのうずめのみこと)を現しています。
三面目の「げんこつ面」は力の神 ③天手力雄神(あめのたぢからおのかみ)で岩戸を開けたところを表現し踊ります。
最後の「鬼の面」は④須佐之男命(すさのおのみこと)を現し、徐々に激しい踊り方になっています。

須佐之男命(すさのおのみこと)は、日本の神話に登場する神で、暴風雨の神として知られています。天照大神の弟にあたる三貴子の一柱で、高天原での乱暴さから追放された後、出雲で八岐大蛇(ヤマタノオロチ)を退治した英雄的な一面も持ちます。その性格は荒々しいと同時に、英雄的な側面も持ち、厄払いの神としても信仰されています。
どろつくどんの起源は、天岩戸神話の物語に重ね合わせて考えることができます。すなわち、五穀豊穣、家内安全、天下泰平を願う奉納行事として行われてきたのです。
保加町どろつくどんの奉納に用いられる四面のお面は、この神話の理解に基づき作られています。すべてのお面は神様を象徴しており、踊り手はその神々の姿を表現する舞を伝承してきました。
各町内で踊り方や表現の伝承に多少の違いはあるものの、先人たちは歌舞伎や能を基本とした舞をさまざまな方法で次世代へと伝えてきました。その光景は遠い昔も同じであったと想像させ、今も変わらぬ伝統の尊さを感じさせます。
- 未来への語り部 ― 伝統をつなぐ若衆たち ―
保加町の法被について - 保加町の法被をご覧ください。背中には丸ほの文字が入り、前の左胸には「保加若」と記されています。保加町の法被を着る者は、すべて保加若として、保加町どろつくどんに関わる者とみなされます。
- 現代では法被はチームや仲間の象徴として使われますが、保加町どろつくどんでの法被は、作法や流儀を老若男女問わず守ることを意味します。
- 秋祭りとしての装いではありますが、市内を角付けしたり欄干橋を上り下りする際には、汗まみれになることもあります。そのため、法被を方袖羽織のまま着たり、脱いでしまうこともあります。しかし、奉納などの神事の際には、全員が法被を正しく羽織り、頭に鉢巻も巻かない正装状態で臨むことが掟とされています。これも、受け継がれた伝統と考えています。