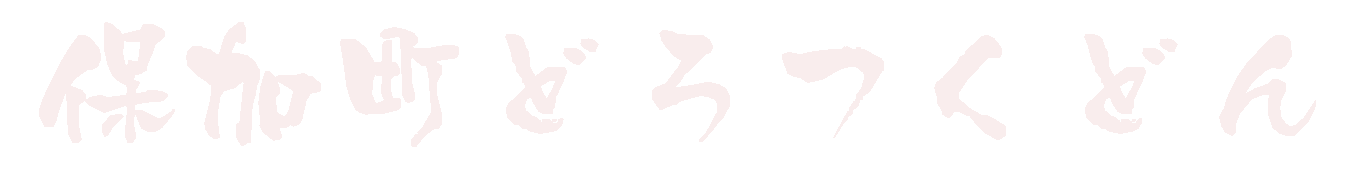──「おにぎえ(御賑会)」──
福岡県柳川市に鎮座する三柱神社は、初代柳川藩主・立花宗茂公、その夫人・誾千代姫、そして宗茂の岳父・戸次道雪公の三柱を御祭神と仰ぐ歴史ある社です。
その秋の恒例大祭「御賑会(おにぎえ)」は、江戸時代より、五穀豊穣や地域の安寧に感謝し、神様を喜ばせるために町をあげて「大いに賑わおう」という趣旨で始まりました。
名称の「おにぎえ」は、まさに「大賑わい」「お賑わい」が語源とされ、町内・商家・若衆・女衆らが山車を曳き、囃子を鳴らし、踊り・御神幸行列を繰り広げることで、その名を体現してきました。
祭りの中心として奉納される山車・囃子「どろつくどん」は、太鼓とドラの激しいリズムに合わせて踊り手が身を乗り出すその勇姿から、福岡県の無形民俗文化財にも指定されている伝統芸能です。
現在でも、あなたがこの祭りの地を訪れれば、「町全体の熱気」「神々への感謝」「地域の絆」が交錯するその場に立ち会うことができます。
保加町どろつくどん
- 「どろつくどん」は、三柱神社保存会(福岡県 柳川市)などが秋季大祭 御賑会(「おにぎえ」)で奉納している山車・囃子の芸能です。
- 保加町はこの「どろつくどん」を構成する町の一つとして重要な役割を持っています。
- 北川新十郎は、1820年代にこの「どろつくどん」の山車・囃子体系を考案・奉納した中心人物の一人です。
🕰 どろつくどんの起源、保加町・北川新十郎の関与
- 「どろつくどん」の起源は、文政8年(1825年)〜文政9年(1826年)頃、三柱神社が現在地へ遷座した際の造営・奉納行事中に生まれたと言われています。
- 保加町(外町)に属する問屋・町人街が、この遷座式の機会に「山車を出して興を添えよう」と働きかけ、のち、各町内が参加した。
- 北川新十郎(保加町所属)および弥永久右衛門らが、江戸・神田明神の「葛西囃子」や京都の山鉾構造を参考に、山車と囃子を刷新。翌年の奉納で大好評を博し、以降「どろつくどん」として定着しました。
🎭 その後の展開
- 保加町が「どろつくどん」の当番町の一つとなり、毎年交代で山車を出す構成となっています。
- 山車構造や囃子体系も整備され、現在は大太鼓・小太鼓・横笛・ドラ・鉦(保加町では摺り鉦)などの五楽器がお囃子を担い、舞手・踊り手とともに山車上で演じられます。
- 北川新十郎という名前は、町史・祭り史の中でこの節目を作った功労者です。
📄 保加町どろつくどん~町を元気に!
保加町において、1826年(文政9年)の三柱神社遷座式に際し、町内問屋・北川新十郎らが江戸の葛西囃子と京都の山鉾を参考に創意を凝らし、山車「どろつくどん」と新たなお囃子を奉納しました。この奉納が祭り行列の先頭を飾る「どろつくどん」の原型となり、以後、保加町は担い手町の一角としてその伝統を守り継いでいます。